
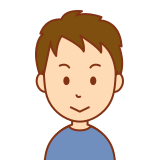
印刷のこれからを考えてみたいと思います。
沈みゆく技術
聖書から始まり、人間の文化が発展発達する横には必ずと言っていいほど印刷技術がありました。それは物語であったり、歴史の口述であったり、マニュアルでした。

最初は手彫りの凸版で、ほぼ版画の技術で出来上がっていました。しかし技術がどんどん発達していくと、文字だけでなく模様、模様だけでなく絵画等の美術としての利用が盛んとなって、それに伴い印刷だけでなく印刷周辺の技術も大きく発展してきました。例えば製本技術や金箔貼りなどです。

しかし、近年デジタル技術の成長が指数関数的に伸びてきているので、デジタルが紙媒体の補完となる流れとなっています。PDFはその代表的な技術ですが、意識するしないは関係なくもう誰でも使えるようになっているし、e-book規格を利用したデジタル書籍は当たり前。漫画や文庫本にあってはe-bookの方が売れているタイトルも多く、AmazonではKindleがネイティブな方も多いのではないでしょうか。
そういうこともあり、印刷業界は斜陽産業とも呼ばれる部類に、(悔しいけれど)いつの間にか入っていて、これからどうしたらいいんだろうかと暗中模索がここ10数年以上続いているというのが、今の印刷業界の本音のところでしょう。
マーケティング
印刷業界で働いたことがある方でしたら、大なり小なりで関わったことがあるお仕事の種類で言うと、一番は名刺、二番はチラシ印刷かもしれません。チラシ印刷は、スーパー等の流通業を相手にしている印刷会社にとっては、長年ドル箱としてとても良いお仕事で、多くのクライアントとして持たせてもらっていたはずです。

しかし、10数年前に出てきたネットチラシがそのビジネスモデルを大きく変えてしまいました。クライアント側はそこそこ積極的とは言えないけども「これからはインターネットだね」という合言葉の元で販促手段にネットチラシを試し始めると、もう今では手放せないツールとなってしまい、場合によっては紙を削減してネットに集中する、という流れも出来上っています。
当初は、PCを使えるアーリーマジョリティのみの相手だったネットチラシも、スマホの普及と回線の高速化によって、今では当たり前、無いとクレーム対象にもなりかねません。
リーチのタイミングとターゲット
マーケティング用語でリーチというのがあります、これは商品やサービス情報がお客様に届き、普通のお客様候補から見込み客に変わる動きのことを言いますが、Webと紙ではそもそもターゲットが違うのでリーチに至る動きが違ってきます。
これはどちらの方向からマーケティングの動きを見るか、によって結論が変わりますが、紙媒体→Webで見るとWebは邪魔でしょうがない。せいぜいQRコードからのキャンペーン誘導的なことぐらいしか考えられなくて、思考も狭くなりがちです。
でも、Web→紙媒体の流れで見ると逆転現象が起きる、つまりワクワク感が止まらなくなる。
Webから紙へ
例えば、仮に物販サイトがあったとしましょう。
世の中には多くの物販サイトがあります、楽天やYahoo!ショッピング、Amazon等のプラットフォームや、ZOZOTOWN・ナイキ等の各ブランドが持つ直販サイト、そして諸々の大小からなるサイトがありますね。
それらの物販サイトの共通の課題として「カート落ち」というのがあります。
サイトを回遊し、レコメンド商品も見て、決め打ち、衝動買いなども含めて、一旦カートに入れてから精算するという流れが一般的ですが、物理的なお店ではカートに入れた時点で99%以上の高い確率で購入は決めています。しかし、Webの場合はカートに入れるのは「忘れないようにする」という意味があったりする。最終的にカードなり代引きなりの支払い方法を選択して、決定ボタンをポチッとするまでは買うかどうかははっきりしないのです。この状態で結局買わずにいるのが「カート落ち」と言われる現象です。
デジタルな施策で、登録メルアドに「カートに入ったままですよ、買わないんですか?」的なものを送って購入を催促する流れはあるけども、読者諸君でそのメールに従った方は果たして何人いるのだろうか?
メールでのDMと紙のDM
カート落ちをしてメールDMでもびくともしない方々へのマーケティング戦略は、今まではメルマガ等による「購入しないと損」だとか、「残り何個になりました、お急ぎください」という煽り文句による販促活動がメインだったんですが、そこに今までとは違う目線を持ち込めるのがWeb目線を持った印刷職人です。
ロイヤリティとホスピタリティ満載の紙の威力を知るその印刷職人は、メールの代わりに紙の印刷物を送ることを考え、しかもカート落ちしたと判断されてから24時間以内に本人の手元に届く仕組みを作りました。そうすると、想像以上のカート落ちからの改善効果が見られるようになりました。
現状、印刷物の生き残りはそこにあると思います。
生き残り&成長戦略
物販サイトの戦略部門に対して、カート落ちの回復戦術としての紙媒体を提案しましょう!
なんて酷いアドバイスはいたしません。これでは今と変わりないのです。何をすればいいのか?というと目線を紙媒体からではなくWebからの目線に変えるということです。
Webからの目線に変えるということは、カート落ち対策を考える事ではなく、カート落ちになってしまうサイト構造の問題点を浮き彫りにさせるということなんです。
Amazonで何か購入したことはあると思いますが、Amazonでものを購入するハードルって、はっきり言ってすごく低いですよね。プライム会員になってカードも登録していると、Kindleなんかはいつの間にか買ってた!という体験のある方は多いと思います。これをデジタルマーケティングではユーザーエクスペリエンス(UX)と呼んだりしますが、アナログな印刷会社に足りないのはこの思考です。
デジタルだろうがアナログだろうが、エンドユーザー、ご購入されるお客様は気持ちよく買いたいという欲求があります。気持ちよく買いたいとは、太鼓持ちがおだてて持ち上げて買わせるのではなく、自分が欲しいものをできるだけスムーズに購入できることを、手元に届くまでを含めて心地よくしたいことを意味します。

売る仕事と作る仕事は別、だという考えだからこそ斜陽と言われるのです。Webマーケティングのマーケティング担当者が四六時中考えているのはエンドユーザー様のUX、購入体験をいかに自然に快適にしていくか?ということなんですよ!
※Web目線でマーケティング思考を巡らせている先駆者「株式会社goofの岡本社長」、私の尊敬する大先輩であり目標となる人物です!
結論
これから生き残る印刷会社はWebマーケティングが得意になっている!
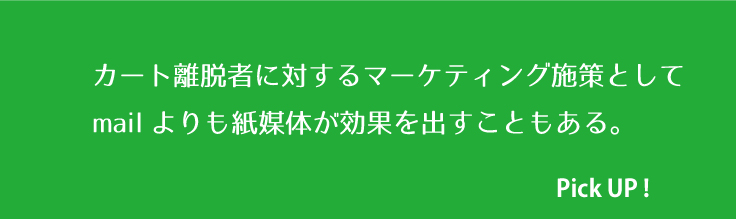
コメント